佐賀・JAさが青果物コントロールセンター
トラック運転手の時間外労働の規制を強化する「物流2024年問題」に対応するため、JAさがは、物流拠点の「青果物コントロールセンター」を立ち上げ、輸送費の高騰を抑えながら、消費地への安定供給を維持する。同センターがJA管内産青果物の集出荷を管理し、多品目を混載することで、トラックの積載率は従来の60%程度から80%超に向上。出荷量が減る端境期でも高い積載率を維持できており、物流の効率化とコスト削減につながった。

管内の集出荷を管理 物流窓口も一元化
JAさがは「消費者に好まれるおいしいトマト」をモットーに大玉、中玉、ミニを年間1754t出荷(23年度)する。他の青果物と同様に関東と関西向けが全体の6割を占め、残りが九州各県の市場で取り引きされる。
県全体の面積の65%を占める同JA管内。トマトの栽培地域も広く、共同選果場が2カ所と個選集果場が4カ所ある。従来は選果場や集荷施設ごとにトラックを手配し、個別に集出荷業務にあたっていた。別々の選果場から同じ市場へ配送されるケースもあり、配送車両が増え、トラックの積載率も下がり、輸送コストが上がる要因にもなっていた。
集出荷を管理する青果物コントロールセンターは、24年問題への対応として、青果物の安定供給に加え、輸送コストの抑制で生産者への影響を最小限にするため、23年10月から佐賀市の物流倉庫を活用し本格稼働した。稼働に先立ち、22年にJA全農グループの全農物流と業務委託契約を締結。同社を窓口として物流業者との契約を一元化し、エリアを越えた範囲で最適なトラックの配車を可能とした。
県内産のトマトやキュウリなど約20品目を九州各県、関西、関東方面へ出荷する。トマトは集荷後に同センターに一度集められるケースもあれば、選果場を回ったトラックが全国各地の市場へ直行するケースもある。集荷量に応じて同センターが効率的な方法を判断し、全農物流が出荷を担う。

予冷で出荷調整に余裕も 青果物セットで販路拡大
同センターのある物流倉庫には15度の低温貯蔵庫と5度の冷蔵庫があり、各選果場から集荷した青果物は基本的に貯蔵庫で一時保管する。鮮度を保ったまま、青果物は当日の夜または翌朝に各地へ出荷する。リードタイムが延びることによる影響はほとんどなく、余裕のある出荷調整が積載率の向上につながっている。
量が少ない場合は、他の青果物と混載して出荷するなどの対策が奏功し、配送する車両数を減らす一方、積載率が向上。今年は以前より20ポイント程度高い80%超の積載率を維持している。
混載で佐賀県産青果物のセット販売が容易になったことで、小ロット品でも無駄なく取引が成立するようになった。市場も、複数の青果物をまとめて納入できる仕組みを歓迎しているという。

物流2024年問題
慢性化していた運転手の負担軽減を目的に、2024年4月からトラック運転手の残業時間の上限が年間960時間となったことで、輸送能力の低下が懸念されている。物流業者は輸送スケジュールやドライバーの待遇見直しを迫られ、生産現場でも集出荷体制の改善や運賃の値上げなどが求められている。

全農物流の職員(佐賀市で)
集荷に合わせた収穫 生産者理解が後押し
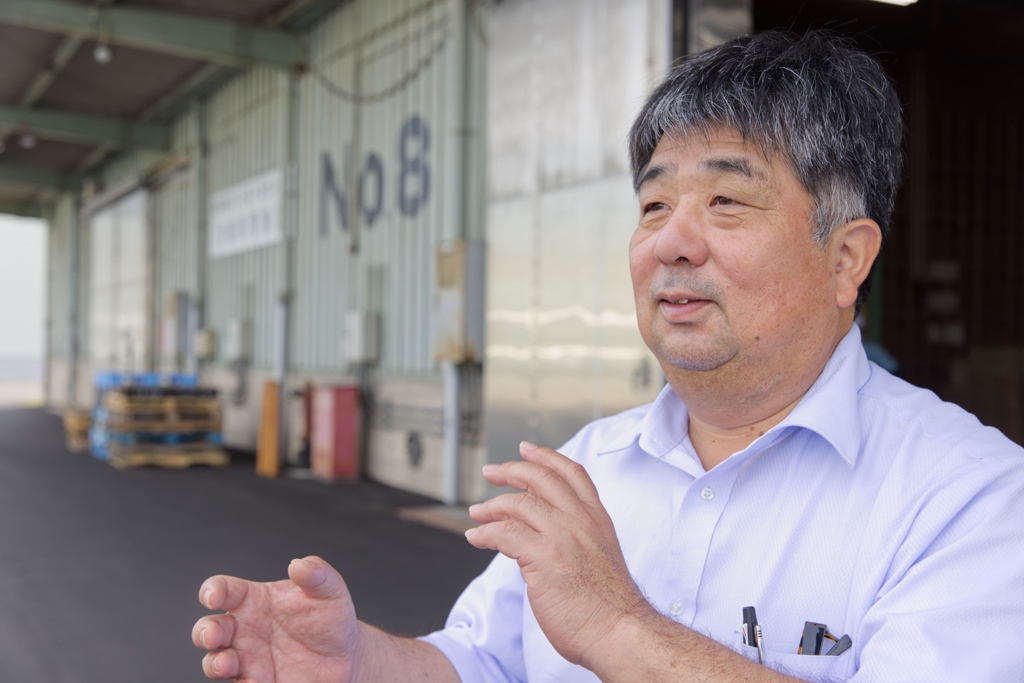
JAさが青果物コントロールセンター 中溝雄一郎センター長
青果物コントロールセンターの立ち上げは、青果物を安定供給するための取り組みだったが、県産農産物のセット販売の増加など、思わぬ効果があった。
また、効率的な集荷ルートをつくるには、集荷時間に合わせた収穫作業が必要で、場合によっては生産者にこれまでのやり方を変えてもらう必要があるなど、ハードルもあった。センターでの集出荷管理の取り組みは、部会と生産者の理解なしには成立しなかった。
積み下ろし作業もドライバーの労働時間に含まれるため、作業時間を短縮させる工夫も必要だった。生産者が安心して営農に専念できるよう、引き続き青果物を確実に消費地へ届けるための努力を続けていきたい。

